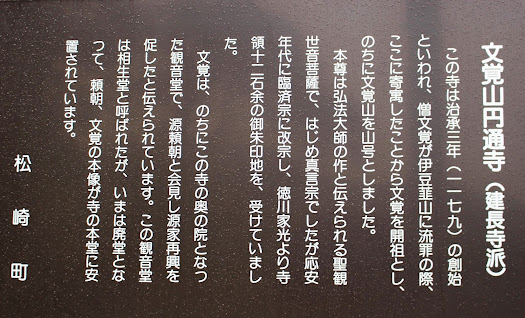文覚がとってきた院宣と彼の叱咤激励により、平家打倒の挙兵へと傾く頼朝。
周到に文覚や安達盛長らと、伊豆や相模、上総等の坂東の豪族の支援の約束を取り付けることに奔走します。
そんな中で、有名な以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)が、伊豆の頼朝の元にも下されるのです。
1.以仁王の令旨
 |
①以仁王
wikipediaより |
鹿ケ谷事件以後、後白河法皇と平清盛との対立はますます険しくなります。そして治承3年(1179年)11月、清盛は数千の兵を率いて京に入り、後白河法皇の院政を強制停止させます。(治承三年の政変)
平家に反抗的な摂政・藤原基房(もとふさ)を大宰府へ左遷、太政大臣以下39名の公卿を解任と政体崩しを徹底します。
更には後白河法皇を鳥羽殿(とばどの)へと押し込めてしまうのです。
源頼政(よりまさ)と一緒に文覚に平家打倒を説いた藤原光能(みつよし)も、この時解任されています。
◆ ◇ ◆ ◇
このような非常事態に大反発したのが、後白河法皇の皇子・以仁王です。(絵①)
以前のブログ「頼朝杉⑦ ~髑髏と院宣~」でも触れておりますが、以仁王は、父である後白河法皇の妻・滋子によって、天皇の継承権をはく奪されるという不遇な道を歩まされているのです。(系図②)
 |
| ②以仁王は見事に皇位継承路線から外されている |
以仁王は、源頼政を頼りとします。
そう、今までこのブログに何度も登場して頂いた鵺(ぬえ)退治の頼政です。頼政に以仁王は言います。
「朝議にあって三位という最高位の源氏である貴殿が、清盛打倒に立ち上がれば、日本全国津々浦々の平家に恨みをもつ源氏諸氏が決起し、容易に清盛は滅ぼすことが出来ると考えるが、如何か?頼政。」
以前もお話しましたが、頼政は権威と女には、めっぽう弱いのです。皇族である以仁王に「源氏の最高位にいる頼政」と言われれば
ーそうか。俺が今の源氏の中ではNo.1なのだな?ー
と少しは気分がいいはずです。
しかし、自分を三位にしてくれたのは、その以仁王が滅ぼそうと言っている清盛なのです。ただ、この後詳細を述べますが、1つ大きな平家の横暴事件が息子の仲綱(なかつな)に降りかかり、頼政も頭に来ているのも事実です。以仁王もそれを知っているからこそ、きっと頼政が平家打倒に賛同すると踏んでいるのです。
頼政は、やはり葛藤します。
そして流石老練な頼政、平家打倒に協力するも、自分が前面に出ない、いざとなったら逃げを打てる方策を考え付きました。
「分かり申した。ではこの頼政、全国津々浦々の源氏が決起する際には、この老体(この時77歳)に鞭を打って、陣頭に立ちましょう。
ただ、まず間違いなく全国の源氏が決起する必要があります。そのためには、私が何某かの御教書(みぎょうしょ:三位以上の地位にある人が主の意思を奉じて発給する文書)を出すよりも、以仁王さまが令旨(りょうじ、皇太子ならびに皇太后・皇后等の命令を伝えるために出される文書)を発出する方がよかろうと存じます。
またこの令旨を頼政配下ではなく、隠遁している源氏の者に全国津々浦々に伝えさせましょう。この頼政が動くと目立ちます。」
2.頼朝への令旨
 |
③『平家物語絵巻』「源氏揃えの事」
以仁王の令旨を諸国の源氏に伝え
歩く源行家と従者
(林原美術館所蔵) |
この令旨を全国の源氏に伝え歩くメッセンジャーの役割をしたのが、頼朝の父・義朝の弟・源行家(ゆきいえ)です。(絵③)彼は生来交渉力があり、扇動者としての才と権謀術数に長けていたとの評価がありますが、やはりその行動は人と人とのコンタクトですから、平家側へバレちゃうのですね。
まあ、行家が令旨を届けた後、各地で挙兵準備をしている間に、このような動向は平家に漏洩するのは当たり前です。
しかしながら、発覚する時期がもう少し後であれば、まだ計画的に頼政や以仁王も対応することができたのでは?また、源頼朝や土佐冠者(とさのかじゃ)こと源希義(まれよし)等ももう少し兵力を集め、緒戦の敗戦は無かったのではないか?等色々と想像してしまいます。頼政も77歳の老齢で皺腹掻っ捌くことも無かったかもしれません。
話を戻します。
頼朝のところには、治承4年(1180年)4月24日に届けられました。
「吾妻鏡」には、「そのとき頼朝は水干(すいかん)を着用して恭しく石清水八幡宮を遥拝(ようはい)してから令旨をおしいただき、披閲(ひえつ)した。」とあります。
以仁王の令旨を拝受したこの時、初めて頼朝が挙兵を決意したようなことが書かれている物語は沢山あります。ところが、頼朝は既にこの時、挙兵準備から1年8か月程も経っていたのです。
それは「吾妻鏡」にも彼が令旨を拝したのは、蛭ヶ小島ではなく、守山にあった北条館で受けたことからも、分かります。既にこの頃、北条時政らと挙兵プランを練っている最中だったと思われます。(写真④)
 |
④守山八幡宮(頼朝挙兵前の館)
|
そして頼朝は新たなる決起の心構えと武運長久を祈った願書を記し、日胤(にちいん)に送るのです。3.日胤
日胤は、挙兵にあたり頼朝が味方に引き入れることを重要視した千葉常胤(ちば つねたね)の息男です。
彼は園城寺(おんじょうじ)の僧となり、頼朝の祈祷僧を務めていました。(写真⑤)
 |
| ⑤園城寺(滋賀県) |
頼朝のために石清水に千日参籠して祈祷していた最中に、頼朝が送ってきた先の新たな願書を受け取ったのです。
それは丁度600日目の参籠の頃でした。
ということは、既に1年半以上前から、日胤は頼朝のための千日祈祷に入っていたことになります。先に述べた通り、既に頼朝は挙兵プランを始動しており、北条館でそのプランを練る一方で、前回のブログで述べましたように伊豆や相模、房総半島に至る各地の豪族への支援要請に文覚や安達盛長らを奔走させていたのでしょう。
ブログ「頼朝杉⑨ ~過去の誓い~」でも触れましたが、そもそも日胤に千日祈祷をさせたきっかけも、後白河法皇の院宣を取り付けた文覚が、頼朝に働きかけたことによると、文覚研究の第1人者・山田昭全氏はその著書の中で述べています。
また日胤に対しても、文覚はその兄・千葉胤頼(たねより)を介して知り合っていた可能性が大きいです。胤頼については、また後ほど書きます。
4.戒め夢
源行家から令旨を頂いた頼朝は、ちょうど相模の国の渋谷重国に支援要請から帰ってきたばかりの文覚を北条の守山館へ呼び寄せ、以仁王の令旨を見せます。
 |
| ⑥挙兵時に活躍する源仲綱 |
「これはまた、以仁王も思い切ったことをされたものですな。以仁王が不遇だったことは、佐殿(すけどの、頼朝のこと)も良くご存じでしょう。京からの三善(みよし)康信殿からの定期的な通信文書にも津々その状況は記載されておりましたからな。
先日、渋谷重国殿のところで、久しぶり会った私の古巣の渡辺党の一人から、ここ伊豆の仲綱殿が、かなり拙い諍いを平家の宗盛(むねもり、兄・重盛亡き後は平家総大将となる人)殿と引き起こしたと聞いております。そのあたりで、もし以仁王が、仲綱殿とその父上・頼政殿を焚きつけたとすれば・・・。」(絵⑥)「だとしたら何だというのじゃ、文覚。」
「以前、佐殿には私が福原に後白河法皇の院宣を拝受してきた折、夢の中に御父上の義朝殿のシャレコウベが現れ、『頼政と一緒に挙兵してはならぬ』と言った戒め夢を見たお話をさせていただいたかと存じます。」(ブログ「頼朝杉⑦ ~髑髏と院宣~」参照)
「ああ、確かその後、藤原光能に夢の解説をしてもらったと言っておったな。頼政の挙兵は『軽挙妄動』になる可能性があるからだろうとな。」
「はい、まあ今回の愚かな平家との諍いを聞いていても、頼政・仲綱らは一時的な感情に流されがちなのが気になります。行家殿など源氏一族に令旨の伝達を任せる等、雑説(情報)漏洩も心配ですね。令旨で決起を促された全国の源氏が立ち上がる前に、清盛に知られ、以仁王が攻められた時、頼政は以仁王を冷静に見殺しにできますかな。無理でしょうな。きっと以仁王を助けるために無謀な挙兵をするでしょう。その動きこそ『軽挙妄動』ではないかと。」
「頼政は清盛に気に入られ、長年四位だったものを、平家以外の武家としては珍しい三位になる引き立てをしてもらったのに、何故に反乱の狼煙を上げるのだろう。文覚どんな諍いだったのだ?」
「つまらない話ですよ。」
と言って文覚が話をし始めました。
5.名馬を巡る諍い
平家物語にもあるこの話。なんか子供の喧嘩のようなお話です。
さて、源頼政の嫡男である伊豆守・仲綱は、京で「木の下(このした)」という名馬を持っていました。
 |
| ⑦平宗盛 |
伊豆の牧の郷には工藤家・狩野家が名馬を沢山もっており、その中の名馬は頼朝も馬好きにするほどのもので、当然、伊豆守である仲綱にも献上していたという訳です。
そこに、平清盛の三男である宗盛(むねもり)が、仲綱に「評判の名馬を見たいものです。」と使者を送ってきました。(絵⑦)
すると仲綱は
「最近、木の下に乗り過ぎてしまったため、知行国の伊豆へ送り休養させております。」
と返事をします。ところが、他の平家の人たちが、「え?木の下は昨日も仲綱が庭で乗り回していましたよ。」とか「今日もいるのを見ています。」等の報告が続々。
まあ、それだけ人に見せたくも、渡したくもない程、仲綱は木の下を愛していたのでしょう(笑)。
しかし、宗盛は「下手に出ているのになんという男だ。」と激怒。
「その馬を所望する」と強く出てきました。
当時、重盛と宗盛は父・清盛と後白河法皇の間に入り、両者の間を取り持つのに腐心していたのです。平家の長者である重盛は、清盛とはまた違う気性で、後白河法皇への忠も建てよう、清盛への孝も建てようと生真面目にやり過ぎたせいで病死してしまいました。
宗盛は重盛程、長者の風格は無いがため、ストレスも重盛程は溜めなかったのでしょうが、流石に知行地・伊豆の国衙(こくが)にも行かず、頼政の基で「木の下」と遊んでいる仲綱に内心イライラする思いだったのでしょう。しかも、「平家にあらずんば人にあらず」の絶頂期に平家No.2の宗盛に嘘までつくとは。
毎日「木の下を譲れ!」と8回も文を送ってきたようです。ストーカー並みです。
まあ、仲綱もあまり賢いやり方ではないですね。ここで良識のある父・頼政が出てきて
「たとえ黄金を丸めて作った馬であっても、そこまで欲しがるものであれば、宗盛殿へ譲ることを惜しむべきではない。お前は一度、伊豆の国衙に戻り、牧の郷で新たな良き馬を見つければ良いのだ。」
と諭します。
「父上がそうおっしゃるのであれば・・・・」
ということで渋々、木の下を宗盛に送るのです。1首歌を添えて。
 |
⑧「仲綱」と焼き印された木の下
※山下景子氏「イケメン平家物語」より |
戀しくは きてもみよかし 身にそへる
かげをばいかゞ はなちやるべき訳:それほど恋しいならば,こちらへ来て見られるがよい。私の身に沿って離れぬ影とも言うべきこの鹿毛を,どうして手放す事が出来ようか。
※『かげ』に『影』と『鹿毛』を掛ける
仲綱も未練がましい気がします。何も言わずスパッと渡せばいいものを。まあ、馬を持ったことはないので分かりませんが、そんなに惜しかったのでしょうね。
◆ ◇ ◆ ◇
この歌を見た宗盛はまた激怒。
「おお、確かにあッぱれな馬や。馬はまことによい馬だが、あまりに主(仲綱)が惜しむので、主の名を金焼(焼き印)にせよ。」
と部下に言い、「仲綱」という焼き印を押します。(絵⑧)
そして、客人が来るたびに
「世に聞こえたる名馬を見てくだされ」と言うと、従者に「その仲綱めに鞍置いてひきだせ。」 そして客人に「仲綱めにお乗りください。仲綱めの尻に鞭を打ってください!尻っぺたひっぱたいてください!」
と木の下を虐め抜いたのです。これを聞いた仲綱が男泣きに泣いたのは言うまでもありません。
頼政も流石にこれには閉口し、静かに平家に対するリベンジを考えるのでした。
6.頼政と同時には挙兵せず
「流石にそんなことだけで、頼政殿が反乱を起こすとも思えんが・・・」
「勿論、これは横暴な平家の振舞に対する1例に過ぎないのだと思います。ただ、平家の連中は、源氏がどれほど侮辱されても仕返しできまいと思っている とか、戦えば十中八九我々は負けるだろう、しかし勝ち負けの問題ではない とか 一寸の虫にも五分の魂 等の発言をその者は頼政と仲綱との会話できいております。累積した鬱憤を考えると頼政殿は挙兵するのでしょう。」
「文覚、それを聴いていたのは誰か?」
「はっ、頼政の部下集団である渡辺党一人・渡辺競(きおう)です。渋谷重国に身を寄せている近江源氏の佐々木氏に20年以上前から頼まれていた先祖代々から伝わる鎧兜を届けに来ていました。生きている間に佐々木氏との約束を果たしたのでしょう。直ぐにまた頼政殿の基に戻り挙兵に備えるようです。」
「うーむ」
頼朝も以仁王と頼政の挙兵が間近に迫っていることを感じました。
ー行家叔父の行脚による令旨の布告なぞ、誰かが直ぐに平家にタレこむ。これで平家の手入れでもあれば、即挙兵に転じるな。ー
「この辺りが動機だとすると、頼政殿らも少し考えが甘いのです。そもそも権威指向の頼政殿は以仁王への期待が大きく、また以仁王は、平家以外の武家に設定されていた四位の天井を突き破った頼政殿に期待する。双方が双方に期待すれば、結果は双方が双方に失望するのが古今東西の習わし。」
と文覚は決めつけます。
「しかし、それでは以仁王が倒れたら、この令旨はどうなる。令旨を発出した本人がいなくなれば、無効になるのではないか?」
 |
⑨千葉常胤
(猪鼻城) |
頼朝は心配顔です。「いえいえ、令旨が無効になるということはござるまい。万が一、そのようなことを主張する御仁があっても、我々には後白河法皇の院宣がございます。」
ーそうか。そういえば文覚が伊豆を脱走し福原まで行ってとってきた院宣があったなー
石橋を叩いても渡らないタイプの頼朝。ここまで確認して少しホッとします。
「頼政殿はいつ頃挙兵すると予測する?文覚」
「はっ、ここ1,2か月内には。令旨交付は絶対漏洩します。いや、もう漏洩しているかもしれません。」
「となると、挙兵は5月~6月頃となるわけだな。では、我々が旗揚げできるのはいつ頃か?」
「まだ半年は欲しいところです。北条、狩野、天野は勿論、三浦、土肥、比企は説得できたものの渋谷は中立です。伊東、大庭、畠山、江戸はダメです。せめて後、千葉常胤(つねたね)殿は説得してからでないと。早くて10月頃かと。」(写真⑨)
「うーむ」
頼朝はまた腕を組んで考え込みます。
文覚は続けます。
「一昨日、京にいる千葉常胤の六男・胤頼(たねより)に文で、一言常胤殿への参陣説得を依頼しております。胤頼殿は私の父の推挙により、上西門院で私と一緒に滝口の武士として仕えておりました。その時に私とは師弟の関係を結んでおります。私がここ伊豆に流される時も、私に同心する旨誓ってくれた信用置ける人物です。私も彼と同行して下総の常胤殿を説得したいと考えています。」
「分かった。ことを急いでくれ。頼政殿との挙兵一致は残念ながら無理だな」
7.頼政挙兵(前編)
文覚の予想通り、頼朝のところに行家が来た一週間後の5月初めには、平家側へ令旨の件は露見していました。
5月15日には、平家が糸を引いて以仁王の臣籍降下を発令、以仁王をひっ捕らえに兵を屋敷に向かわせます。
 |
⑩女装をして園城寺へ向かう以仁王
(月岡芳年画) |
この時点では頼政の関与は平家側に察知されておりません。頼政自身が前面に出ない方策が功を奏しているのです。この時点で「挙兵失敗」と判断し、頼政は平家側に寝返る方法も選択しえたのかもしれません。ところが仲綱は「木の下」の恨み一直線です。平家の兵が以仁王の屋敷に着く前に以仁王に知らせるのです。以仁王は女装をして、日胤の手引きにより園城寺へ逃れます。(絵⑩)
16日、平家は園城寺に以仁王の引き渡しを求めますが、園城寺はこれを拒否。更に延暦寺、興福寺にも協力を呼びかけます。
21日、平家は宗盛以下の一門+源頼政を大将とする園城寺攻撃軍が編成されます。この時点でも頼政はまだ清盛恩顧の忠臣とみなされているのです。
ところが、仲綱が黙っていません。
「父上、木の下虐待をお忘れか。あの時、父上も涙を流し、平家の横暴を一緒に嘆いてくださったではござらんか。」
「・・・」
その日の夜、頼政は自宅を焼き払い、仲綱と約50騎を率い、園城寺に入りました。(360度写真⑪)
⑪園城寺から琵琶湖、比叡山方面(左側)を臨む(360度写真)
この以仁王・頼政の挙兵により、これから壇之浦合戦まで連綿と続く「治承・寿永の乱(いわゆる源平合戦)」の火蓋が切って落とされたことになるのです。
先に出てきました文覚の古巣・渡辺党の1人、渡辺競(きそう)。この挙兵で胸のすくような動きを見せ、仲綱と木の下の恨み返しをしますので、次回もお楽しみに!
ご精読ありがとうございました。
《続く》
【守山八幡宮】〒410-2122 静岡県伊豆の国市寺家1204−1
【園城寺(三井寺)】〒520-0036 滋賀県大津市園城寺町246